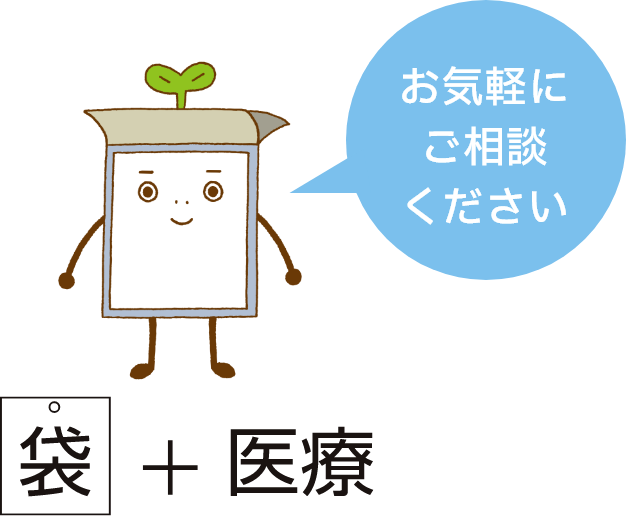社長メッセージ
わたしの人なり・考え方

わたしの人なり・考え方
会社を継ぐ(PR会社からの転職)
私が育った環境は、まさに典型的な町工場の家庭でした。1階が工場で、2階が住居。小学生のころ、工場から「かっちゃん(私)、おかえり」とパートのおばちゃんたちが迎えてくれる、そんな日常を過ごしていました。
両親のおかげで大学へ進学し、私は東京でシステムエンジニアをやり、転職して企業や自治体の広報サポートの仕事をしていました。
当時は父の会社を継ぐことに抵抗を感じていました。自分には別の道があると思っていたのです。しかし、20代後半に実家に戻った際、工場で働くスタッフたちの様子を目にして大きな衝撃を受けました。彼らは目を輝かせ、楽しそうに、そして純粋に仕事に取り組んでいたのです。
その姿を見て、私は初めて「本当に健全に働く」ということが、どういうことかを感じました。当時、メディア関係の仕事で、そこそこの成果を出していたものの、モヤモヤしていた自分がいました。もっと自分が本当に価値を感じることに没頭したい、そんな想いが強まっていたのです。
実家に戻り、父やスタッフが誠心誠意働く姿を目の当たりにしたとき、自然と「一緒に仕事をしてみたい」と思うようになりました。けれど、前職での経験と比べて、大阪の片田舎にある町工場の環境に馴染めるのか、職人たちとのやりとりに不安もありました。彼らは、仕事帰りにパチンコに行ったり、大酒を飲んだりして、ケンカすることもあるような、いわゆる「職人肌」の人たちでした。
しかし、それよりも私に強く響いたのは、父の「誠心誠意」働く姿でした。子どものころからずっと見てきたその姿に触発され、一度父と一緒に仕事をしてみたいという想いが強まりました。

先代から学んだ一人ひとりを大切にすること
親父と一緒に働いてみると、父には父なりのやり方がありました。
正直、父は職人肌ではありませんでした。腕は決して器用ではなかったかもしれません。しかし、父には人を引きつける不思議な力がありました。周りにはいつも協力してくれる人たちが集まり、皆に愛されていたのです。
親父のマネはできないが、教わったことは、人を見ることでした。
父はこう言っていました。「人とやるときは、ここまで言うたら怒りよるとこだけ見とけよ」。その言葉の意味が当時はわかりませんでしたが、今ではこう解釈しています。人と接するとき、その人の心の動きを感じ取り、その人がどんなことに敏感になるのかを見極めることが大切だ。
この教えを基に、私はいつも相手の心の動きに目を向けています。この人は本気で取り組んでいるのか、それとも表面的な態度なのか。モノづくりは人が行うものです。少しの気の緩みや、ほんの少しの妥協、「これくらいでいいだろう」という、よこしまな気持ちが、結果としてモノに現れるものです。
モノづくりは人が行うもの、モノづくりは人づくり。人を大切にしないと、いいモノはできないと私は考えています。人柄がモノに反映されるから。一人ひとりを大切にすることの重要性を、私は父から学びました。

私たちの仕事は感性が大切
私たちの仕事は、料理をするコックの仕事に似ています。特別な大学の学歴がなくても、感性と日々の鍛錬でできる職業だと思っています。1日1日の積み重ねこそが、私たちのものづくりにとって最も重要です。
学校で落ちこぼれてしまっても、たかが小・中・高校の9年間です。大切なのは、これからどういう気持ちで自分の腕を磨いていくかだと考えています。
昔は、親方や師匠と弟子の関係の中で、ものづくりの技術や心構えが伝えられてきました。美容師や料理人、その他の専門職も同じように、仕事ができるようになってから弟子がつき、誇りと威厳を持って仕事に取り組んでいたはずです。
しかし今は分業化、さらには自動化が進み、「こうやっておけば良いだろう」という風潮が広がっているように感じます。そのため、昔と比べて仕事の量が圧倒的に少ないと感じますし、機械化やIT化は便利な面もありますが、人間の感性や技術を磨く機会が奪われている部分もあるのです。
私たちの製造業には、機械やデジタル技術の力が必要です。しかし最終的な微調整は、やはり人間の感性で行う必要があります。基本をしっかり押さえ、丁寧に仕事に向き合うことで、より良い製品が生まれると信じています。

より良いものをつくるために、常に進化し続ける
いいものをつくろうという意識がなければ、進化はありません。昔の職人たちは、その日の状況を見極め、機械を的確に設定していました。私は、若い世代でもそのような職人技に近づけるように、IT化を積極的に進めています。
IT化によってある程度の品質の商品は作れるようになります。しかし、ただ日常業務を「こなす」だけでは、それ以上の進歩は望めません。常に良いものを目指して挑戦し続けることが、進化の鍵です。
1年を通じて日々少しずつでもより良いものを作ろうと努力を重ねると、その積み重ねが大きな結果を生みます。常に進化をし続ける意識をもっていただきたい。

誕生日には祝福を!
一人暮らしを始めて、寂しさを感じていた頃、入社した会社でチームの皆さんがお祝いをしてくれたことを今でも覚えています。
誕生日に誰からも何も言われず、寂しい思いをしていた若い私を、チームが温かく祝ってくれた。それがとても嬉しく、心に残っています。
だからこそ、私はスタッフ一人ひとりの誕生日に、同じ仲間としてプレゼントを贈っています。
日々の感謝と、これからの期待を込めて、毎年プレゼントを選びます。喜んでもらえるかなと考えながら、贈る瞬間が私自身も楽しみなんです。

上田食堂
この取り組みのきっかけは、スタッフが「ろくなものを食べていない」と感じたことでした。
食べないと活力は湧きません。活力をみなぎらせるには、まずはエネルギーが必要です。
そこで、毎月2回、ランチの時間に「上田食堂」を開催し、スタッフの胃袋を満たす試みを行っています。健康が第一ですから、食事を大切にすることが、仕事のパフォーマンスにもつながると信じています。

お互いを知る社内行事
小さな会社の大きなメリットは、社長と社員の距離が近いことです。しかし、会社が成長し規模が大きくなるにつれて、社員と直接交流する機会が少なくなってしまいます。
そのため、作業場とは異なる場面で、いつもと違う景色の中でお互いを知ることが大切だと考えています。その一環として、バーベキュー大会などの社内行事を定期的に開催しています。
たくさん話す必要はありませんが、同じ時間を共有することで、社員同士が自然とつながる場を作りたいのです。小さな組織だからこそ、社員の結びつきが大きな力になると信じています。

ホームベースになりたい
私たちの会社は、「ホームベース」になりたいと思っています。
いつでも「ここにあるよ」と言える場所。もし誰かがさびしくなったら、帰ってこれる場所でありたい。
会社を辞めた社員たちも、何かのタイミングで戻ってこれる、そんな温かい場所をつくりたい。そのために会社を今以上に成長・発展させていかねばなりません。

最後に、こんな未来を作りたい
私たちの目指す未来は、50人規模の町工場のモデルケースとなることです。
最新のIT技術やデジタル化を活用しながらも、人間関係を大切にし、人が中心にあるテクノロジーを取り入れた会社です。そして、もっと医療の役に立ちたいと思っています。
医者や看護師にはなれなくても、医療や感染管理に興味がある方なら、ぜひ一緒に働きませんか?
当社の仕事は機械を使った作業が中心なので、力がなくても問題ありません。老若男女問わず誰でも十分に活躍できる環境です。私たちと一緒に、医療サプライヤーのプロフェッショナルとしての地位を築いていきましょう。皆様からのご応募をお待ちしています。

プロフィール
代表取締役 上田克彦
趣味はマラソン
なぜ、マラソン?とよく言われます。健康のために始めたマラソン、年齢を重ねるごとにドキドキやワクワク感が少なくなり、日々の生活に張り合いがないと感じる中、マラソンの大会前の準備や、走ることに熱中することで、再び「わぁ~」という感覚を取り戻すことができました。
マラソンは一見個人競技のようですが、実はチームプレーです。ボランティアの方々の応援があって成り立っており、時には一緒に走るおじちゃん、おばちゃんからの「がんばれ~」という声が支えになっています。やっぱり、僕はチームプレーが好きなんです。
(ベストタイム 3時間59分)
新しいモノ好きです
左腕にはAppleウオッチ、右腕にはランニングウォッチをしています。
好きな食べ物
バナナ(必ず、毎週一房は購入、見てどれが美味しいか分かるぐらい食べています)
好きな言葉
当たって砕けろ。でも今は、いまは当たっても砕けない。日々全力投球